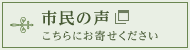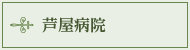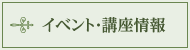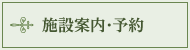ここから本文です。
更新日:2025年12月1日
児童手当
児童手当は、高校生年代までの子どもを養育している人が受けることができる手当です。
お知らせ-令和6年10月に児童手当法が一部改正されました
【制度改正に伴う新規申請の受付は、令和7年3月31日で終了しています】
- 申請が必要と思われる方には、令和6年9月上旬、令和7年2月上旬に案内通知を送付しました。ただし、市が対象者を把握できない場合(子どもが別世帯の場合や市外居住で芦屋市に住民票がないなど)は、通知できませんので、ご自身で確認の上お手続きをお願いします。申請が必要か不明な場合はお問合せください。
- 市から通知が届いた場合でも、受給資格者が公務員の場合は、勤務先で手続きの要否を確認のうえ、手続きをしてください。
- 新制度の概要は以下のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童を高校生年代まで延長
- 第3子以降の支給額を3万円に増額
- 多子加算のカウント対象を大学生年代まで延長
- 支給月を偶数月(年6回)に変更
- 申請が必要な方
・令和6年9月までの制度で所得上限額限度額を超えているため児童手当を受給していない方(新規)
・現在児童手当を受給しておらず、高校生年代の子を養育している方(新規)
・大学生年代の子を養育しており、その子を含めて3人以上養育している方(増額)
- 申請が不要な方
・令和6年9月までの制度ですでに受給中で、高校生年代の子が対象になることにより増額となる方(ただし芦屋市に住民票がない場合などは、手続が必要です。ご不明な場合は、こども支援係にお問い合わせください。)
・令和6年9月までの制度ですでに受給中で、支給額の変更や所得制限の撤廃により増額となる方
令和6年10月支給分(6月~9月分)は、改正前の手当となります。
改正前(令和6年9月分まで)の制度について(別ウィンドウが開きます)
多子加算の申請手続きについて(令和7年3月卒業)
申請のご案内
令和7年4月以降引き続き多子加算の算定を受けるために、申請が必要な方には令和7年3月上旬に案内通知を送付しました。
申請が必要な方は、多子加算の算定対象となっている18歳年度末(高校卒業)を迎える子がいる受給者、22歳年度末までの子が短大等の卒業を迎える受給者です。
案内通知に記載の方法で、期限までに申請手続きをしてください。
令和6年度の制度拡充以降の申請手続きについて
オンライン申請のご案内
芦屋市電子申請システムによる便利なオンライン申請をご利用ください。
- 免許証やマイナンバーカードなど本人確認ができる書類をご準備ください。
- 新規請求(申請)の方は通帳など振込口座の確認できる書類をご準備ください。
- 10~20分程度で申請完了します。
新規請求(現在児童手当を受給していないかた)
▶新たに児童手当を受給するための申請はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
窓口・郵送により申請書を提出される場合
申請書や書き方をダウンロードし送付していただくか、直接こども支援係の窓口にお越しください。
対象者
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人が対象です。令和6年10月分から所得制限が撤廃されました。
- 手当は、父母が共に児童を養育している場合は、所得の高い方に支給します。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。留学のために海外に住んでいて、一定の要件(期間は3年以内、児童のみ留学等)を満たす場合は支給対象になります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設等へ支給します。
- 公務員(独立行政法人等を除く)は、勤務先からの支給になります。手続方法等は勤務先へお問い合わせください。
支給額(月額)
| 区分 | 児童手当 |
|---|---|
| 3歳の誕生日月まで | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳の誕生日の翌月から高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
- 第3子以降とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
支給の開始
原則として、申請した月の翌月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受け取れなくなりますので、ご注意ください。
- 異動日(出生・転出予定日・公務員退職日等)が月の後半の場合、申請が異動日の翌日から15日以内(15日目が土日・祝日の場合は、次の平日まで)であれば、異動日の翌月分から支給します。
- 里帰り出産等により、窓口で手続きができない場合は、申請書をダウンロードし、郵送(必着)で申請してください。申請書のダウンロードページへ。
- 令和6年度の制度拡充の対象のかたについては、特例により令和7年3月31日までの申請により、令和6年10月分まで遡って支給されます。
支給日と支給方法
偶数月の15日に、その前の2か月分を受給者名義の口座に振り込みます。
(配偶者や児童名義の口座には振り込みできません。)
15日が土日祝日の場合は、直前の平日に振り込みます。
改正前(令和6年9月分まで)の制度について(別ウィンドウが開きます)
申請の手続き
- 初めての子どもが生まれたとき(出生)
- 他市区町村や国外から芦屋市に引っ越してきたとき(転入)
- 児童手当の受給者のみ国外転出し、配偶者と児童は国内に残るとき(受給者の変更)
- 児童手当の受給者が公務員(独立行政法人等を除く)でなくなったとき
- 認定請求が却下(受給資格が消滅)となったあとに、所得が所得上限限度額を下回ったとき(令和6年9月分以前)
- その他、離婚や婚姻等により、新たに児童手当を受けられるようになったとき
申請が完了してから約1~2か月後に、児童手当の受給資格が認定された方には認定通知書をお送りします。
申請に必要なもの
【申請者本人が申請する場合】
- 認定請求書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
- 申請者の本人確認書類(下記参照)
- 申請者・配偶者等の個人番号確認書類(下記参照)
- 3歳未満の児童を養育している方で国家公務員共済・地方公務員等共済に加入の場合は、申請者の健康保険情報がわかるものの写し(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面等)※郵送の場合は被保険者等記号・番号等をマスキングしてください。
- 児童の大学生年代の兄姉等を含めると、3人以上の子どもがいる場合は、監護相当・生計費の負担についての確認書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)と兄姉等の個人番号確認書類(下記参照)
- 児童と別居している場合は、別居監護申立書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)と児童の個人番号確認書類(下記参照)
- 公務員(独立行政法人等を除く)でなくなった場合は、退職の辞令または勤務先からの児童手当支給事由消滅通知書
- 状況により、他にも書類が必要な場合があります。
【代理人(同一世帯の方以外)が申請する場合】
- 上記1、3、4(該当する場合は5、6、7も提出)
- 委任状(様式不問ですが、ダウンロードまたは窓口で取得可)(別ウィンドウが開きます)
- 代理人の本人確認書類(下記参照)
本人確認書類
次のいずれか1つを窓口で提示してください(郵送の場合は写しを提出)。申請者本人が申請する場合は申請者のもの、配偶者等を含む代理人が申請する場合は代理人のものをご用意ください。
- 個人番号カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
個人番号確認書類
次のいずれかを窓口で提示してください(郵送の場合は写しを提出)。申請者・配偶者等それぞれ必要です。また、申請者が児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類も必要です。なお、芦屋市に住民票がある場合は、ご提出いただかなくても構いません。
- 個人番号カード
- 通知カード(住所が住民票と一致している場合のみ。個人番号通知書は確認書類として使用できません。)
- 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
変更の届出
以下のときは、手続きが必要です。届出が遅れると、手当の支給が遅れる場合や、返還が必要となる場合があります。
| 届出が必要なとき | 必要書類 |
|---|---|
| 2人目以降の子どもが生まれたとき |
1.額改定認定請求書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます) 2.受給者の健康保険情報がわかるものの写し(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面等) |
|
児童の大学生年代の兄姉等を含めると、3人以上の子どもがいるとき |
1.監護相当・生計費の負担についての確認書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます) 2.本人確認書類 |
| 受給者と児童が別居になったとき |
1.別居監護申立書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
|
|
受給事由消滅届(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
|
| 振込口座を変更したいとき | |
|
その他お手続きが必要なとき
|
こども政策課こども支援係までご連絡ください。 |
芦屋市電子申請システムによるオンライン申請も利用可能です(一部手続を除く)
▶出生や別居等により手当の対象児童の数が増減する場合はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
▶振込口座を変更する場合はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
現況届の提出が原則不要になりました
現況届の提出が原則不要となりましたが、次の場合は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な人には、6月上旬に現況届をお送りします。
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者
- 離婚協議中で配偶者と別居している
- 配偶者からの暴力等により住民票の住所地が芦屋市と異なる
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない
- その他、状況を確認する必要がある
離婚協議中で別居している場合の手続き(同居優先制度)
父母が離婚に向けて別居している場合は、生計を同じくしないものと考えられ、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方へ支給する制度があります。
- 離婚とは関係なく、仕事上の転勤等で児童と別居しているような場合は、生計を同じくしているものと考えられるため、同居優先制度は適用されません。
申請することができる方
次のすべてを満たす場合に、申請することができます。詳しくはこども政策課こども支援係までご相談ください。
- 離婚協議または調停中であること(事実が確認できる書類の提出が必要)
- 受給者と別居していること(住民票の異動も必要)
- 児童と同居していること(住民票の異動も必要)
申請に必要なもの
- 認定請求書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
- 申請者の本人確認書類
- 申請者の個人番号確認書類
- 3歳未満の児童を養育している方で国家公務員共済・地方公務員等共済に加入の場合は、申請者の健康保険情報がわかるものの写し(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面等)※郵送の場合は被保険者等記号・番号等をマスキングしてください。
- 児童手当の受給資格に係る申立書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
- 離婚協議中で別居している事実が確認できる書類
- 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
- 調停期日呼出状の写し
- 家庭裁判所における事件係属証明書
- 調停不成立証明書
- その他、申請者に離婚の意思があり、配偶者にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類
児童手当受給証明書の発行
奨学金の申請等で児童手当の受給証明が必要な場合は、振込口座の写しも証明となる場合がありますので、まずは提出先にご確認ください。なお、受給証明書が必要な場合は、申請をしてください。
受給証明書の申請に必要なもの
- 受給証明書交付申請書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
- 受給者の本人確認書類(代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類)
- 受給者本人や受給者と同一世帯の方以外が申請する場合は、委任状
- 使用目的、証明を必要とする年度を記入いただきます。児童手当の年度は8月(令和6年度以前は6月)切り替えです。
- 児童手当受給証明書の発行には1週間程度かかりますので、ご了承ください。