ここから本文です。
更新日:2025年10月11日
地震から身を守るために

日本は、世界でも有数の地震大国と呼ばれており、
これまでに多くの地震や津波による自然災害を経験してきました。
また、30年以内に南海トラフ地震が発生する確率は、
2025年1月の時点で「80%程度」とされています。
一瞬の判断が生死を分けることも考えられます。
落ち着いて行動するために、
地震から身を守る知識や行動を今一度考えましょう。
地震が発生したときの行動

自宅、職場、車内、外出先など、
どのような場所にいる時でも常に身を守るための準備をしておくことが重要です。
落ち着いた行動ができるように、
1つ1つ確認しましょう。
地震発生!(自宅編)
①揺れを感じたり、緊急地震速報を受けた時は、
身の安全を守ることを最優先に行動してください。
近くのクッションなどで頭を守りましょう。
丈夫なテーブルの下や、物が「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」
空間に身を寄せ、揺れがおさまるまで様子を見てください。
②もし料理などで火を使っていた時は、
コンロの火を消し、ガスの元栓を閉めましょう。
しかし、無理をしてはいけません!
揺れがおさまったら
①火が付いたままの場合は、
揺れがおさまってから慌てずに火の始末をしてください。
②ガラスの破片などが散乱している場合があります。
底の厚いスリッパや運動靴を履いて移動しましょう。
③扉や窓を開けて出口を確保しましょう。
この時、慌てて外に飛び出してしまうと、
瓦、窓ガラス、看板などが落ちてくる危険性があります。
④自分自身の安全を確保できれば、
家族や隣近所で積極的に声を掛け合い、
お互いの状況を確認しましょう。
⑤大きな地震の後には余震が発生します。
落下物や倒壊する危険がある場所には近づかないでください。
⑥ラジオなどで情報を確認しましょう。
間違った情報には惑わされないように注意してください。
自宅以外で地震が発生した場合
路上では

手荷物などで頭を守り、近くにある広場等へ逃げましょう。
繁華街ではガラスや看板などの落下物や、
自動販売機の転倒などに注意してください。
住宅街では倒壊の危険性があるブロック塀や石壁、門柱から離れましょう。
車の運転中は

急ブレーキは大事故に繋がりかねません。
ハンドルをしっかりと握って徐々にスピードを落とし、
道路の左側に停車しましょう。
揺れがおさまるまでは車外に出ず、ラジオ等で情報を確認しましょう。
エレベーターの中では

地震時管制装置が付いているエレベーターは、
自動的に最寄りの階に停止します。
装置が付いていなければ、全ての階のボタンを押し、
停止した階で安全を確認した後、エレベーターから降りてください。
電車の中では
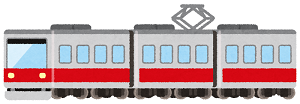
電車は強い揺れを感じると自動的に停車します。
つり革や手すりにしっかりとつかまり、
倒れないように注意してください。
電車が停車して揺れがおさまっても、むやみに線路に降りる行為は危険です。
係員の指示に従いましょう。
家庭での備え
家具
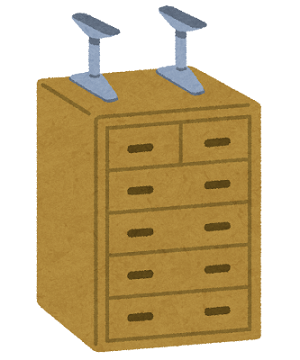
阪神・淡路大震災が発生した時に、
建物の中でけがをした人の46%は、家具の転倒、落下によるもので、
29%はガラスの飛散が原因だと言われています。
つまり、家具をしっかりと固定してガラスの飛散防止対策を施せば、
多くの人は建物の中でけがから身を守ることができます。
ベッドの横や扉の近くにタンスや本棚が置かれたりしていませんか?
今一度、家具のレイアウトを家族で話し合い、
家具や家電を固定するなどの対策を行いましょう。
食料、飲料の備蓄

地震が発生すると、電気、ガス、水道が使えなくなったり、
道路状況によっては物流が機能しなくなるおそれがあります。
そのため、最低でも3日分、
可能であれば1週間分の食品を備蓄しておくことが重要です。
日常生活とかけ離れた事態が起こったとしても、
暖かく栄養バランスのとれた食事があれば、
前向きな思考と活動するエネルギーが湧いてきます。
安否確認方法
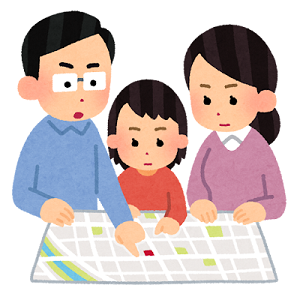
家族が別々の場所にいる時に地震が発生した場合、
お互いの安否を確認したくても電話やインターネットの回線が繋がりにくくなるため、
連絡がとれない場合があります。
事前に避難場所、避難方法、避難経路を家族で話し合い、
それぞれの居場所を把握できるようにしましょう。
また、災害時に安否を確認するサービス等を確認しておきましょう。
◦災害用伝言ダイヤル(171)
大規模な災害が発生した時に、
被災地内の電話番号に限り利用可能なサービスです。
局番なしの「171」に電話をかけると、
安否などの伝言を音声で録音したり、伝言を再生することができます。
◦災害用伝言板
被災地域の方が自らの安否を文字情報によって登録することができるサービスです。
PC、スマートフォン等をもとにして全国から伝言を確認できます。
