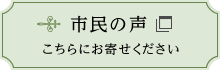ホーム > 教育・文化・スポーツ > スポーツ > スポーツ事業 > 芦屋ゆかりのスポーツ人物・団体像 > 川廷榮一(かわていえいいち)
ここから本文です。
更新日:2021年6月24日
川廷榮一(かわていえいいち)
日本テニスの国際化の”先駆者”
経歴
 国際テニス写真家・ITFオリンピック担当理事
国際テニス写真家・ITFオリンピック担当理事
1933(昭和8)年/兵庫県芦屋市生まれ。中・高・大学とテニスで活躍。同志社大学卒業後は国内でテニス写真を撮り、’68年から海外で取材活動を展開、国際テニス写真家の草分けとなる。’79年以降は連盟活動に専心。アジアテニス協会、国際テニス連盟など多数役職を歴任。オリンピックソウル大会以降、ITFオリンピック担当理事として北京大会まで5回のオリンピックテニス運営を担当。その功績により、2012年国際オリンピック委員会オリンピック功労賞を受賞。また、長年の貢献により、オールイングランドテニスクラブ(ウィンブルドン)名誉会員に推挙される。旭日中綬章、国際テニス殿堂ゴールデン・アチーブメント賞など多数受賞。2013(平成25)年8月3日永眠。享年79歳。
カメラマンとして世界のテニスを日本へ
川廷榮一のテニス人生の始まりはフリーランスのカメラマンだった。同志社大学でプレーした後、繊維関係の家業を継いだものの、テニスへの想いは捨てがたく、その道を歩み始めていた。テニスを撮りはじめた動機は「一般プレーヤーの参考になるフォームを記録したい」であった。カメラ機材は今とは異なるフィルム時代である。スーツケースいっぱいにフィルムを詰め込み、二眼レフのカメラを抱えて家を出ていく父親の姿が、3人の幼い子供たちにはサンタクロースのように見えたという。国内での撮影をはじめて13年、1968(昭和43)年、日本プロテニス界のパイオニアとして活躍した石黒修(元デビスカップ代表。俳優・石黒賢の実父)が豪州への遠征を計画し、それに川廷を誘ってくれた。かねてから海外の本格的取材を望んでいた川廷には、願ってもない好機であった。この1968(昭和43)年は、全スポーツ界の中で画期的なオープン化が実現している。かつてはアマチュア大会として開催されていたテニスのグランドスラムは、アマチュアとプロの垣根がなくなったのである。川廷は、オープン化で激動する世界のテニス界を取材しては、スポーツ誌、写真展、出版などを通して、日本に情報を発信し続けた。1975(昭和50)年の澤松和子(現吉田)とアン清村によるウィンブルドン女子ダブルス優勝のころには、海外写真の多くを手掛けている。一瞬を切り取った迫力に「写真の力ってすごい」と思いながら、国内のテニス活動の国際化に大きく貢献していった。世界各国のテニス界の現状と変革を取材するうちに、川廷は、次第にテニスの世界すべてに関心を抱くようになった。世界のテニスを日本に紹介したいとの思いから写真を撮り始めていたが、テニスの普及、発展を考えるならば、テニスの裏側を知る必要があると考えたからである。協会組織や大会運営、コートや付属施設等など興味は尽きなかった。その結果、カメラマンの領分を越えて、国際テニス組織に関わることとなったのである。
芦屋の川廷宅で歓待された世界のトッププレーヤーたち
1933(昭和8)年、川廷は兵庫県芦屋市で生まれた。父が清水善造(日本テニスの黎明期を築いた名選手)と懇意だったことから、自宅コートにはデビスカップ選手などがよくテニスをしていた。高校時代は松岡功(元デビスカップ選手。松岡修造の実父)に負けたことがないというのが川廷の自慢だった。芦屋の自宅には多くのトッププレーヤーや関係者がやって来た。わずか18歳にしてグランドスラム初優勝を果たし、全仏でも優勝を飾ったケン・ローズウォール、ウィンブルドンと全米オープンの2大会で、プロアマ両方のタイトルを成し遂げたジョン・ニューカム、オープン化後の女子初となる年間グランドスラムを達成したマーガレット・スミス・コート、グランドスラム14勝を誇るオーストラリアのイボンヌ・グーラゴング等など、川廷宅で食事をしたり、近所の鉄板焼きのお店に連れて行ったり、家族総出で草の根の交流を紡いできた。
中韓スポーツ交流の道を開く”テニスのかけ橋”
1984(昭和59)年2月1日、ロンドン市郊外のウィンブルドンにあるITF(国際テニス連盟)のオフィスに、遠く北京から一通のメッセージが届いた。「私たち(中国・韓国)のデビスカップ2回戦の試合を、香港(協会)で開催できないため、わが協会はこの対戦を中国・雲南省昆明市で開催することに決定しました。」中華人民共和国テニス協会事務局長からの簡潔な英文メッセージは、中華人民共和国と大韓民国との間に直接的なスポーツ交流の道を開く歴史的内容であった。国交のない両国のスポーツ交流は、政治的にも大きな歴史的意味を持つものであった。「中国が受けてくれた韓国選手が中国へ行ける!」川廷の脳裏で、3年前にこの計画を意識してから数々の出来事が、走馬灯のように回転した。川廷は、真っ先に報告しなければならないITF会長のフィリップ・シャトリエ氏が川廷をITFの代表として、この交渉を一任してくれたことを思い出した。国際的にも強力なテニス界の指導者であるシャトリエ氏に、川廷は機会あるごとにアジア地域の協会活動を見ることを提案し、日本をはじめ、中国、韓国、インドネシアなどの関係者と有意義な話し合いを行ってきた。シャトリエ氏の右腕として、最前線で尽力した。1ドル(360円)の国際化を生きたフリーランス出身の現場の苦労や努力は、日本ではなかなか評価されず、悔しい思いもした。そして同年3月、ついにデビスカップ東洋ゾーン準々決勝に参加する韓国選手団8名が、中国・昆明市に到着した。韓国のスポーツ選手が中国入りしたのは、これが初めてである。韓国選手団が参加するにあたり、韓国を承認していない中国国内で公式に「韓国」の呼称が使用されるのも初めてである。緊迫の中で開幕した試合も、懇親会では両国の選手や関係者たちが何度も杯を交わし、お互いの健闘を讃えあった。この10年、スポーツが政治の横暴に苦しめられる中で、いつになく世界の注目を集めるこの大会、中でも焦点は中国選手団の参加であった。政治の壁を突き崩す最強の武器がスポーツである。川廷は、それを証明するために中韓両国のスポーツ交流に道を開いたのである。
アジアに種をまき、理想のピラミッドを目指す
国際テニス界のオープン化以来40年間に、約75か国・地域へ400回の海外出張をし、600の競技大会や220回の会議などに従事してきた。これらの仕事を続けてきて、川廷にはある時期から考えが固まってきたことがある。テニスにもいろいろな世界がある。満足なボールもラケットもないレベルから、高額の賞金が賭けられたトップクラスまで、みんなテニスなのだ。川廷たちの目的はテニスの裾野を広げ、発展させていくことである。どの世界も重要で、力を尽くさなければならない。ただ、心の中では、開発途上国の子供たちにスポーツで希望を与えたい。コートも何もない国に行って、「テニスというスポーツを知っていますか、一緒にやってみましょう」と、一つの種蒔きをする。その芽の育つ過程が一番楽しく、やりがいを感じるという。1995(平成7)年ころ、世界のテニス連盟の中で、アジアが最も理想的な道を歩んでいるという評価が生まれつつあった。伝統のあるヨーロッパと違い、アジアのテニスはレベルが様々で対応が難しかったが、それが実りつつあったからである。川廷は、働いてくれるアジアの若者たちにいつもこう話していた。「僕らの時代というのは、近代テニス100年の歴史に乗っかった10年、20年で、そこからまた無限に続いていく。このわずかの期間を歴史に良い時代として残せる仕事をしよう。」と。アジアのテニスはこの20年間に発展したと言われれば本望だった。各国でテニス人口が広がり、トップは世界レベルの選手、その中にはプロもいればアマもいる、あらゆるテニスがある理想的なピラミッド、まさに一時代として記憶に残るピラミッドをつくろうというのが川廷の目標であった。
(文責:慶應義塾大学SFC研究所上席所員菅沼久美子)