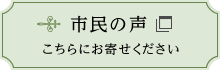ホーム > 教育・文化・スポーツ > スポーツ > スポーツ事業 > 芦屋ゆかりのスポーツ人物・団体像 > 田畑外司(たばた・そとし)
ここから本文です。
更新日:2019年1月29日
田畑外司(たばた・そとし)
芦屋を愛した陸上の投てき名選手
経歴
 お気に入りの芦屋市に長年住み、生涯を終えた元陸上の投てきの名手・田畑外司。現役時代は重さ2kgの円盤を手に日本一になった実績を持つ。趣味として始めたテニスは、芦屋国際ローンテニスクラブでラケットを振り、夫婦揃って楽しんだ。スポーツ界の表に立つことはなかったが、芦屋を拠点にテニスのほか、山を愛して各地の名のある”やま”へ足を向けた。往年の足跡を振り返った。
お気に入りの芦屋市に長年住み、生涯を終えた元陸上の投てきの名手・田畑外司。現役時代は重さ2kgの円盤を手に日本一になった実績を持つ。趣味として始めたテニスは、芦屋国際ローンテニスクラブでラケットを振り、夫婦揃って楽しんだ。スポーツ界の表に立つことはなかったが、芦屋を拠点にテニスのほか、山を愛して各地の名のある”やま”へ足を向けた。往年の足跡を振り返った。
パワーの原点は家業の手伝い
田畑の出身地は山陰の島根県益田市だ。実家は材木商を営んでおり、田畑は幼少のころから家業の手伝いをしていた。重たい木材を運んだりトラックへの積み下ろしに精を出しているうち、自然にパワーが付いた。
肩にはタコが消える間がなかった。「毎日の手伝いがウエイトトレーニングと同じ効果につながったのでしょう」と話す田畑。この実家家業の手伝いが将来花開く源となったのだ。
最初に”材木運び”で蓄えた力が物を言ったのは相撲だった。近郊で行われる相撲大会では負け知らず。「タバタのボンは力持ち」と評判だった。相撲の内容も”技より力”で押した。相撲に次いで野球にも力を入れた。ところが、高2の時にパワーに目を付けられ、陸上の投てきに誘われた。とはいえ、陸上はあくまで余技であり本命は相撲と野球だった。
高2と述べたが、高校は益田高だ。ここで少し回り道を説明すると、田畑の世代は終戦の1947(昭和22)年に実施された教育(学制)改革の煽りを食った時代である。旧制中学生だった田畑も新制高校への移行を余儀無くされたのだ。高3になると、引っ張られた陸上の投てきで頭角を現した。投てきの砲丸投げと円盤投げで島根県大会を勝ち抜いた後、地区大会の中国高校大会で3位に食い込んだ。が、全国大会の大舞台であるインターハイでは入賞できなかった。高校卒業後は進学せず、家業の手伝いをすることを選んだ。この間、ひょんなことから、ある選手の指導を任されることになった。その選手とは潮喬平(益田産業高-現・益田翔陽高)というスプリンターで、後に1956(昭和31)年メルボルン五輪の代表になったほどの選手である。
投てき専門の田畑が、畑違いの短距離選手の指導を、なぜ?と思われがちだが、田畑は「30mダッシュ走では潮に負けたことがない」と話していた。この二人の因縁は後々までつながってくる。
進学後、オールラウンドの練習
陸上の師弟関係にあった田畑と潮は1952(昭和27)年秋の東北国体に島根県代表となって活躍した。潮は19歳未満100mで2位となり、田畑は青年砲丸投げで12m13を突き出し、3位に食い込んだ。田畑については余談がある。田畑の東北国体出場は陸上だけではなかったのだ。相撲にも駆り出され、山形市であった相撲大会の団体戦で日本一の実力者と言われた福岡・景山という選手を下し、やんやの拍手を浴びた。個人戦でも期待されながら以後を棄権。理由は仙台市での陸上会場に移動するためで、夜行列車に揺られて駆け付け、砲丸投げで表彰台へ上がったのだ。東北国体が終わった後、田畑の人生を変える事態に遭遇する。それは国体で活躍した潮のことが新聞で取り上げられ、「潮、中央大学へ」と。潮だけなら分かるが、田畑が驚いたのは「田畑も中央大学へ」の記事が掲載されたのだ。田畑にとっては、まったく身に覚えのないことだった。
田畑は腹をくくった。家族に進学について相談した。父親は「そとし(外司)の名前のように家を出て、外で羽ばたけ」と励まし、進学に賛成してくれた。
1953(昭和28)年の春、晴れて中大に進学。潮とは同学年となったが、潮は年上の田畑を「さん」付けで呼んでいた。事情を知らぬ者は奇異に感じたことだろう。学生生活を迎え、本格的に陸上投てきの練習に打ち込んだ。凝った練習は午前6時の起床にはじまり、6時30分から朝レンを。陸上をベースにした練習は、相撲、レスリング、バスケットボール、ボクシング各部を訪れ、それぞれの練習を吸収するというもの。運が悪かったのは2年生の時、野球をしている最中、ファウルボールのチップが右手中指を直撃。骨折で手術をしシーズンを棒に振った。ケガが原因で「円盤よりも得意だった砲丸の突き出しが思ったようにできなくなった」と、これより後は円盤投げに比重が移った。3年生になると復活し日本選手権の砲丸投げと円盤投げともに3位に入賞した。
あらゆる競技部でのトレーニングを取り入れた成果が現れたとみていい。4年生になると日本選手権と、学生のNo.1を決めるインカレで円盤投げに優勝し、両大会の砲丸投げで2位を占めた。
社業との両立で頑張った社会人時代
中大を卒業すると旭化成に入社した。1957(昭和32)年4月のことだ。そのころの実業団の選手は練習に伴う優遇制度はなかった。旭化成も例外ではなかった。日々の練習は就業時間が終わってからが原則。田畑は入社後、8年間にわたり勤めとの両立で頑張った。
試合では全日本実業団対抗選手権の円盤投げでタイトルを2回取り、1948(昭和23)年から1969(昭和44)年まで行われていた全国勤労者陸上でも優勝している。また余談になるが、当時は試合に行くのも”一苦労”した。例えば旭化成・宮崎県延岡市から東京に行く場合、飛行機や新幹線のない時代なので汽車を利用するほかはなく、急行で約24時間かかった。しかも寝台車や座席指定もなく、座席の確保が大変だった。数人での遠征などは座席の下に新聞紙とバスタオルを敷いて寝る選手も出る始末。そのころを知る人にとっては、なつかしい思い出話になるが、今の若い選手には全く想像もつかない話だろう。
余談のついでに田畑に関してのエピソードを一つ。1959(昭和34)年の夏、神戸市の王子競技場で全国勤労者陸上の第12回大会があり、田畑は円盤投げのサークルに立った。ところが夏というのに、当日はあいにくの雨で気温が低く、ぶるぶる震えながらの競技になった。
と、その当時、学校こそ違え郷里の先輩である吉岡隆徳がスタンドから田畑を手招きした。吉岡といえば”暁の超特急”と言われ、1932(昭和7)年ロサンゼルス五輪の100mに6位入賞した偉大なスプリンターだ。田畑は「何だろう」と思ってスタンドへ行くと、吉岡は「きょうは寒いからこれを飲め!」と、小さなコップにウイスキーを入れて差し出した。田畑は手にすると一気に飲み干した。すると田畑の体から寒さが消え、次の試技で43m19の大会新アーチで優勝したのだ。まさに「酒は百薬の長」となった。
円盤投げと取り組んだ田畑は、国内で行われた国際大会で日本代表として活躍したが、1959(昭和34)年に日本歴代3位となる45m52をマーク。1963(昭和38)年に監督兼副部長に就き、現役としても続行した。秀逸なのは30歳を超え、現役に終止符を打った1964(昭和39)年に45m96(日本歴代10位)の自己ベストのアーチを掛けたことである。監督としての喜びは1964(昭和39)年12月に当時、伊勢路であった第9回全日本実業団駅伝で旭化成のユニホームが躍り、大会新で初制覇した時だ。生涯の喜びとなった。
芦屋の地で静かに眠る
田畑が旭化成に勤めていた社会人現役の時は転勤が多かった。各地の勤務地に赴くうち、田畑が最も気に入ったのが芦屋だった。40歳代のころ、芦屋を”永住の地”と決め、ここから単身赴任で任務の地へと向かった。定年を迎えて指を折ると、芦屋を永住と決めてから50年近くなるだろうか。
芦屋に住みはじめ、陸上現役を離れるとテニスに凝った。テニスは芦屋国際ローンテニスクラブで妻・智恵子とともに会員となって楽しんだ。田畑は定年を迎えると、くる日もくる日もテニスざんまい。「健康のためですよ」と話し、同クラブでの大会で夫婦でラケットを振り、アベック優勝したこともある。
テニスのほか、山岳散策にも精を出した。が、相撲や陸上の投てき選手として鳴らしていた丈夫な田畑だったが、傘寿(80歳)の祝いを境に心房細動が悪化。ついには入院をすることになった。2017(平成29)年の秋から冬にかけて病院生活を送り、72kgあった体重が62kgまで落ちる始末。
退院後は徐々に体力が回復に向かったが、2018(平成30)年の6月中旬に心不全のほか、肝臓、腎臓などが悪化し7月はじめに天国へ旅立った。
85歳4ヵ月あまりの人生だった。交友が多かった田畑の訃報に、惜しむ声が多数寄せられた。弔電の中には旭化成陸上競技部のマラソンで名を高めた、あの宗茂、宗猛のものもあった。
「突然の訃報を聞き、残念でなりません。大先輩として時には優しく、時には厳しく、激励をしていただきました。頑張れたのもそのおかげだと感謝しています。2020東京オリンピックに向けて、チーム一丸で頑張ります」が、宗兄弟の弔電の一部である。妻・智恵子は「(夫は)気に入った芦屋で、好きなように生きたのでは、と思っています」と話す。陸上の元名選手の一人が芦屋の地で静かに眠っている。
(文責:元神戸新聞社運動部長・力武敏昌)
田畑外司『芦屋を愛した陸上の投てき名選手』(PDF:324KB)(別ウィンドウが開きます)