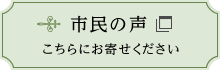ホーム > 教育・文化・スポーツ > スポーツ > スポーツ事業 > 芦屋ゆかりのスポーツ人物・団体像 > 吉川(現・星野)綾子(よしかわ(ほしの)あやこ)
ここから本文です。
更新日:2023年12月14日
吉川(現・星野)綾子(よしかわ(ほしの)あやこ)
「芦屋女子高が生んだ名花」戦後初参加のオリンピック日本代表へ
経歴
 1952ヘルシンキオリンピック競技大会出場(100メートル、走り幅跳び)、芦屋女子高校(現・芦屋学園高校)出身
1952ヘルシンキオリンピック競技大会出場(100メートル、走り幅跳び)、芦屋女子高校(現・芦屋学園高校)出身
1952(昭和27)年7月、フィンランドの首都ヘルシンキで開かれた第15回オリンピック(五輪)競技大会に国際社会への復帰を許された日本が戦後初めて、16年ぶりに参加した。72人の日本代表団の中で陸上競技の選手は男子16人、女子3人の計19人。女子選手の1人が最年少19歳の吉(現・星野)綾子だった。芦屋女子高校(現・芦屋学園高校)を卒業後、帝塚山学院短大に進み、在学中に日本代表に選ばれ、100メートルと走り幅跳びに出場した。
現役時代は陸上界だけでなく、全国のアイドル的な存在だった。その名花のスパイクの跡をたどった。
19歳で憧れの夢舞台へ
北欧の空の下でのオリンピック(以下「五輪」)開会式。「陸上を始めた15歳の時から憧れていた五輪へ」出場できた感動をかみ締めながら、入場行進で足を運んでいた。19歳の乙女盛りの吉川綾子だが、肝っ玉は据わっていた。「日本選手を応援してくれているスタンドの人たちの顔が1人ひとり、はっきり見えた」の半面、近くにいた黒人選手の顔の色が「青みを帯びて見える?」と。「やはり精神的な圧迫を受けているのかな」の緊張感を覚えた。極度の精神的緊張が襲うといわれる五輪の舞台。が、吉川は100メートルと走り幅跳びともに「物怖じすることなく臨めた」と振り返る。試合度胸のよさはビックレースで実証されており、緊張感から金縛りになるのが当たり前の五輪でも「ふだん通りのレースができた」。だが、外国人選手との力量の差は歴然だった。100メートルの1次予選は中盤まで互角にレースを進めたものの、ゴールでは12秒6で落選。走り幅跳びは午前の予選で5メートル4を跳んで、予選ラインの5メートル0を越え、午後からの決勝へ進んだ。決勝での1回目は5メートル54。2回目にスピードに乗った助走を生かし、5メートル80を越えたあたりへ着地した。が、1センチメートルほどスパイクの先が踏み切り板から出てファウル。惜しかった。6位入賞者が5メートル81だったので、ファウルでなかった。結果は5メートル54で16位に終わった。「悔しい。あれだけ辛い練習を乗り切って備えてきたのに。ベストを出し切ることができなかった。あがっていた、とは思わなかったのに」。
国際級のベストレコードを出す
吉川が期待されていたのは、五輪年の6月に5メートル75を跳び、4年前のロンドン五輪の優勝者の記録5メートル69を上回っていたのだ。100メートルは五輪前年の10月、広島国体で12秒0のセンセーショナルなタイムを出していた。この記録は1951年度世界ランク9位に当たり、1928(昭和3)年アムステルダム五輪の800メートルに日本人女性初のメダリスト(銀)となった人見絹枝が保持していた100メートル12秒2を23年ぶりに破ったのだ。吉川が更新するまでに2人がタイ記録を出していたが、壁は厚かった。その壁をついに吉川が破り、走り幅跳びと合わせ、五輪に向けて入賞の期待が持たれていたのだ。吉川の思わくがはずれたひとつは「(日本は)情報不足で世界の”動き”を知る機会が少なすぎました」。世界の陸上界の水準は急速に上がっていて、ヘルシンキ五輪の優勝記録はウィリアムズ(ニュージーランド)の6メートル4。以下、9位までが五輪新を出したのだ。
世界の情報不足はともかく、話を広島国体に戻してみよう。吉川の体調は決してよくなかった。お腹も痛かった。だが、予選の後の準決勝でベストの12秒3が出た。「体調が悪いうえ、軽く走ったのに思わぬタイムが出た。不思議だな」と思いながら走った決勝で、飛び上がらんばかりの記録を生んだのだ。おまけ付きは競技場の施工関係者が「トラックの優秀さを証明してくれた」と、銅製の花瓶を記念品として吉川に贈呈してくれた。
陸上の源は芦屋女子高(現:芦屋学園高校)時代
吉川は1933(昭和8)年3月、大阪市生まれ。5人兄姉の末っ子。父・良一は非鉄金属商を営み、吉川は不自由なく育った。1945(昭和20)年4月、旧制・大阪扇町高女へ入学後、芦屋女子中に転校。学制改革で新生高校発足の1948(昭和23)年、芦屋女子高校1年生として陸上を始めた。
1年生から第1回インターハイに出場した。が、この年は100メートル、走り幅跳びともに決勝進出はならなかった。2年生になると生まれ持った資質が芽を伸ばし、両種目ともに2位につけた。3年生では暴風雨となった大会の中、100メートル13秒1、走り幅跳びは5メートル55の大会新で2種目に全国の頂点へ。200メートルは1位と0秒1差の27秒7で2位となり、たった1人で17点を挙げ、学校対抗で母校を2位の座に。インターハイだけではない。1950(昭和25)年は10月の日本選手権に100メートルで日本一に。走り幅跳びは2位だったが、5メートル64の高校新をマーク。高校生とはいえ、あっぱれな活躍ぶりで五輪候補に躍り出た。インターハイの後、100メートルでは12秒4の高校新を出している。
卒業の月の1951(昭和26)年3月には第1回アジア大会の代表に選ばれ、インドのニューデリーで4×100メートルリレー(3走)で金、走り幅跳びで銀と2つのメダルを取った。ただし、体調は最悪。大会前に盲腸を手術し、10日後に退院して、翌日から練習を再開したものの、いつ切り口が開いてもおかしくない状態で試合に臨んだのだ。意志の強さの証明である。
体が弱かった吉川が五輪代表になるなど、丈夫な身体に育んでくれたのは「芦屋女子中、女子高でした」。理由は「阪急芦屋川駅から六麓荘にある学校まで、毎日50分かけて徒歩通学したおかげ」と。風雨の日も乗り物に乗らず、山道を登下校するのに、粗末だった運動靴は1か月で靴底に穴があいた。六甲山系の山道の登下校がトレーニング場となり、体質改善になったのだ。
恩師と父親の情熱に感謝
在学中に忘れてならないのは、芦屋女子中、高校の5年間、担任と体育の授業を受けた野田弁吉先生の存在だ。御影師範の教諭を経て、芦屋女子高に転勤して陸上部を指導した。「どの先生よりも厳しかった」が、情熱も人一倍だった。1945(昭和20)年半ばといえば食糧事情が悪かった時代。だれもが空腹を抱えていた。だが、野田先生は練習の後、自身で栽培したサツマイモを、夫人が蒸して差し入れ、空腹の吉川たちに振る舞った。「本当にありがたかった」と吉川。恩師は試合の度に資格を持っていた鍼灸やマッサージを施してくれた。今から70年近く前に、こうした施しをマンツーマンで受けたのは「私だけの特権で。本当に恵まれた環境でした」。帝塚山短大1年で、先の広島国体の100メートルで快挙を成し遂げた時、兵庫選手団役員として広島へ来ていた野田先生が、真っ先に吉川のところへ駆け寄った。
「よかった。おめでとう!」と、涙を光らせながら声を掛けてもらった時の「嬉しさは最高だった。これでご恩返しができたかな」。吉川の胸も高鳴った。
一方、父親の愛情は「18足」を数えたスパイクが一つの例だ。そのころはスパイク1足買うにも大変だった。食事難と同時に物資のない時代でもあったのだ。父の良一は娘の活躍に理解を示し、輸入品の困難さの中、カンガルーの皮製のスパイクを与えた。吉川は両親の愛情に感謝の念を今も忘れない。吉川がヘルシンキ五輪へ出場した時は帝塚山短大生だったが、同短大には陸上部はなかった。あえて吉川が同短大に進学したのは「父が陸上が全てではない。女性としての素養を身につけなくては」の助言によるものだ。同短大ではたった1人の陸上部で、インターカレッジ(日本学生陸上競技対校選手権)の100メートル、200メートル、走り幅跳びで大活躍し、オールドファンにはなつかしい部旗揚揚と、校歌吹奏があった。同短大では吉川の活躍を想定して、部旗・校歌を急いでつくった逸話が残っている。新しい短大だったので、部旗も校歌もなかったのだ。
「花の散り際は潔く」。引き際の決断は早かった。短大卒業後、芦屋女子高で週4日授業を持ち、誘われるまま産経新聞大阪本社の記者として、3日間活動する”変則”な社会生活となった。この期間は長くはなく、読売新聞で健筆を振るい、後に世界のマスコミ界でも稀なIOCメディアトロフィーを受賞した星野敦志氏と結婚。主婦として日本陸上競技連盟の中で、陸上界に貢献した。現在は東京都内在住。母校、芦屋学園の陸上復興を心より願っている。(文責:元神戸新聞社運動部長力武敏昌)